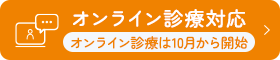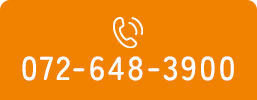ちょっと気になる”糖尿病”のお話②
2025.10.30
こんにちは。松本ほがらかクリニック阪急高槻市駅前の渡邉です。
前回は「糖尿病ってどんな病気?」について解説致しました。今回のテーマは、健診や血液検査でよく目にする「HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)」についてです。
HbA1cとは、「過去1~2か月の平均的な血糖の状態」を反映する指標です。
血液中の赤血球にはヘモグロビンというタンパク質があり、そこにブドウ糖(血糖)が結びつくと「糖化ヘモグロビン(=HbA1c)」になります。血糖が高い状態が続くほど、このHbA1cが高くなる、つまり“ここ最近の血糖コントロールの通信簿”のような数値なのです。
食後やストレス時など、一時的に血糖が上がることは誰にでもあります。しかしHbA1cは短時間の変動には左右されず、過去の積み重ねを反映します。そのため、日々の努力の成果や、逆に治療の見直しが必要かを判断するうえで、とても重要な指標になります。
一般的に、健康な方のHbA1cは5.5%前後。糖尿病の診断基準は6.5%以上とされています。
ただし、目標値は人によって異なります。年齢、合併症の有無、低血糖のリスクなどを総合的に考えて決めていくことが大切です。
当院では、HbA1cの変化をもとに、食事・運動・薬剤のバランスを一緒に見直していきます。
「HbA1cが上がった」「健診で高いと言われた」という方も、焦らずまずは原因を一緒に探してみましょう。
継続的なフォローをしていくことで、自分に合ったコントロールを私たちがお手伝いをいたします。
次回は「血糖値が上がりやすいタイミング」についてお話しします。どうぞお楽しみに。