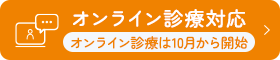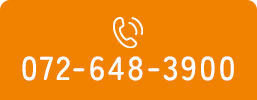- 内分泌について
- 内分泌疾患のタイプについて
- ホルモン分泌の仕組みについて
- 下垂体で分泌されるホルモンについて
- 先端巨大症(末端肥大症)
- クッシング病
- プロラクチン産生腫瘍
- 非機能性下垂体腺腫
- 下垂体機能低下症
- 尿崩症
- 副腎偶発腫瘍
- 原発性アルドステロン症
- クッシング症候群(ACTH非依存性)
- 褐色細胞腫
- 副甲状腺機能亢進症
- 甲状腺機能亢進症・バセドウ病
- 破壊性甲状腺炎
- 甲状腺機能低下症・橋本病
- 甲状腺腫瘤
- 甲状腺ホルモン異常による不妊症
- 骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
内分泌について
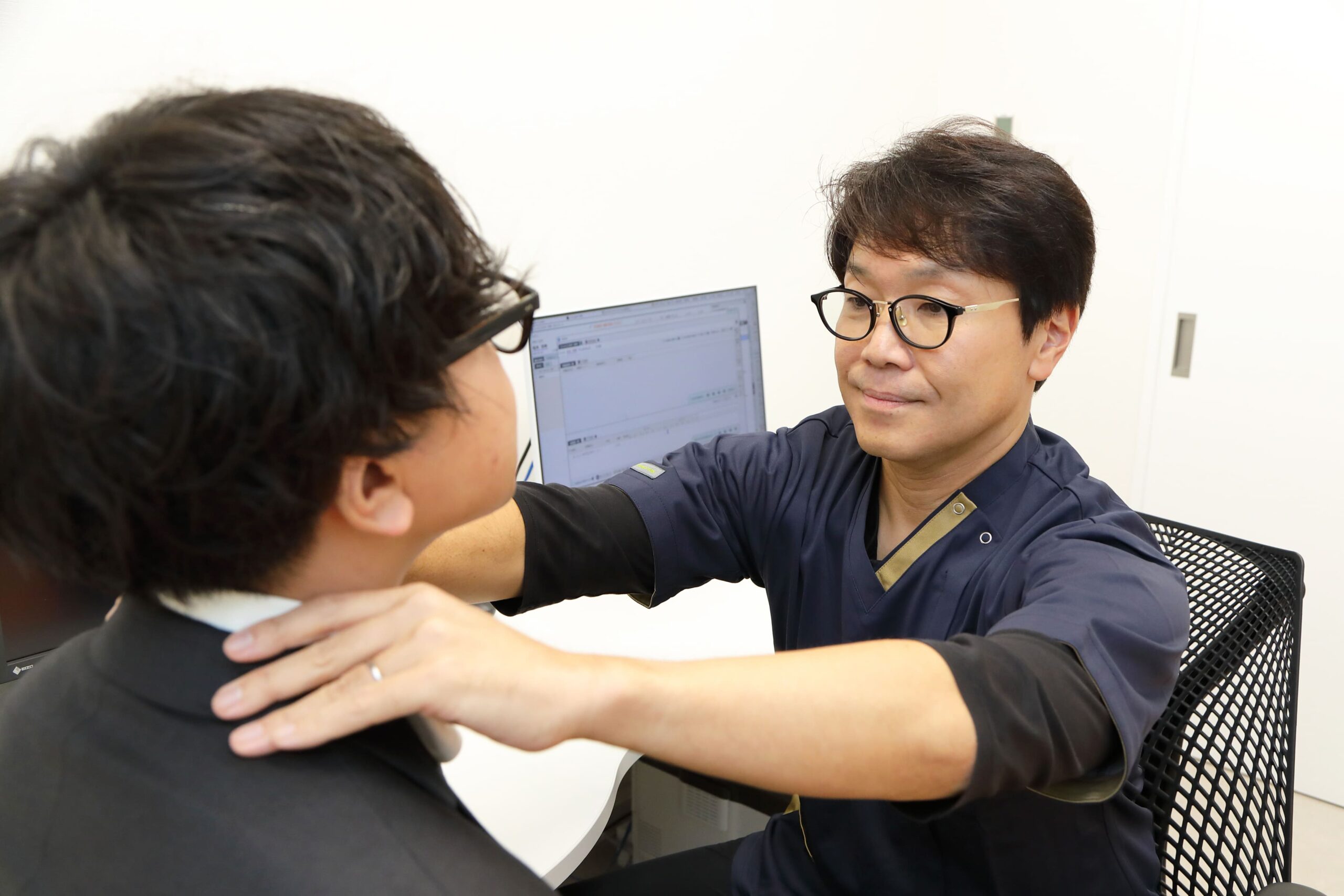
内分泌という言葉は、多くの方にとってあまり馴染みがないかもしれません。ただ、多くの方が「ホルモン」と聞けば理解するかと思います。内分泌は、ホルモンによって刺激されて、細胞が活性化したりリラックスしたりする体内の働きを指します。
ホルモンを分泌する器官を「内分泌器官」と呼びます。視床下部、脳下垂体、甲状腺、副腎、卵巣や精巣、そして胃腸、心臓、脂肪細胞などの臓器や組織にて、内分泌器官は生成されます。
内分泌器官で生成・貯蔵されたホルモンは、必要に応じて血管を通じて、遠隔の標的細胞に作用し、また近くの細胞に直接送り届けられます。
これらのホルモンは、体温や血圧などの恒常性を維持し、成長、発達、生殖行動、エネルギー代謝、運動機能、精神活動など、生体を健康に維持するために幅広く作用します。内分泌に異常が生じると、体内の様々な機能に影響が現れるため、内分泌のメカニズムや体調の変化について理解しておくことが重要です。これが、内分泌内科が「内科の中の内科」と称される理由です。
内分泌器官の異常による内分泌疾患は、異常が生じた場所によって異なるため、その原因を十分に鑑別しながら治療に取り組むことが非常に大切です。
内分泌疾患のタイプについて
内分泌疾患には、次のように、
- ホルモンの過剰分泌
- ホルモンの分泌不足
- 内分泌器官にできた腫瘍
3つに分類されます。
内分泌器官の異常は、一般的には見逃されやすい疾患であり、「体調不良が続いているな」と軽く考えられがちです。体調不良を感じる際は、内分泌内科を受診してみることをお勧めします。
適切な検査と総合的な診断を組み合わせ、適切な治療を続けていけば、内分泌疾患は良くなっていきます。
ホルモン分泌の仕組みについて
 ホルモンは、視床下部、脳下垂体、甲状腺、副腎、卵巣、精巣などの内分泌器官だけでなく、心臓、腎臓、膵臓、脂肪細胞など、沢山の器官で作られている物質です。生成されたホルモンはそれぞれの器官で蓄えられ、必要に応じて主に血管を通じて、ホルモンを必要とする器官へ届けられます。
ホルモンは、視床下部、脳下垂体、甲状腺、副腎、卵巣、精巣などの内分泌器官だけでなく、心臓、腎臓、膵臓、脂肪細胞など、沢山の器官で作られている物質です。生成されたホルモンはそれぞれの器官で蓄えられ、必要に応じて主に血管を通じて、ホルモンを必要とする器官へ届けられます。
これらのメカニズムを調節しているのは、視床下部と脳下垂体です。視床下部は脳下垂体をコントロールし、脳下垂体が全身の末梢内分泌器官を管理しています。
このように、詳細かつ階層的に管理されているホルモンは、全身の恒常性維持(体温や血圧などを一定に保つ機能)、代謝、成長・成熟、生殖、ストレス応答など、色々な身体機能をコントロールしています。上から下への指令が伝わる構造である一方、下流の器官がホルモン分泌状況に応じて、分泌と供給をコントロールする側面も存在します。
これらのバランスが微妙に関連し合い、体全体の正常性が維持されるようなシステムになっているのです。
下垂体で分泌されるホルモンについて
下垂体は脳の真下に位置しており、前葉と後葉に分かれている器官です。前葉は、視床下部からの刺激により、成長や身体の恒常性、生殖に不可欠なホルモンである「副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)」「成長ホルモン(GH)」「甲状腺刺激ホルモン(TSH)」「黄体形成ホルモン(LH)」「卵胞刺激ホルモン(FSH)」「プロラクチン(PRL=乳腺刺激ホルモン)」を分泌しています。
後葉では、体内の水分損失を防ぐ抗利尿ホルモンであるバソプレシン(AVP)と、分娩や乳汁分泌に関連するオキシトシン(OXT)が生み出されています。
先端巨大症(末端肥大症)
先端巨大症(末端肥大症)は、下垂体に発生する良性腫瘍によって成長ホルモンの過剰分泌が引き起こされ、その結果、手足や顔の特徴的な変化が生じる疾患です。発症が成長期に起こると、身長が伸び過ぎることもあります。見た目の変化が大きいため、家族の指摘を受けて気づくことが増えています。
発症後、適切な治療を受けないまま放置すると、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの合併症が現れる可能性があります。さらに、手足の関節に変形性関節症が発生し、これらの合併症が脳血管障害や心血管障害を引き起こしやすくなります。
先端巨大症は珍しい疾患ですが、手足や顔の変化は少しずつ進むため、ご家族ですら発見しにくい可能性もあります。もし以下のような症状がいくつか該当する場合は、ぜひ内分泌内科を受診してください。
- 指先が太くなる
- 靴のサイズがきつくなる
- 唇、鼻が太くなる
- 舌が大きくなって話しにくくなる
- 下顎が突き出る
- 眉毛が盛り上がる
- 手の平が常に汗をかいている
- 頭痛が頻繁に起こる
- 今までより性欲が減る
- 月経異常が起こる
この病気の治療は、全ての腫瘍を取り除く手術が成功すれば、完全に治癒できる見通しがあります。手術の方法は確立されており、比較的安全に行われますが、大きい腫瘍で手術に適していない場合や、深刻な合併症がある場合は、薬物療法が導入されます。症状が薬物療法で上手くコントロールできない場合は、放射線療法が選択される可能性があります。
ただし、骨が異常に大きくなっている場合、治療により合併症やその他の症状は改善されるかもしれませんが、外見上の問題は回復が難しいかもしれません。それ故に、早期に発見して治療を行うことが肝要です。
この病気は日本国内では指定難病とされているため、治療費の補助を受けることが可能です。
クッシング病
クッシング病は、副腎皮質ホルモンが脳下垂体の良性腺腫により、過剰に分泌されることによって引き起こされる疾患です。これにより、様々な症状が生じる可能性があります。また、腺腫は稀に悪性化するケースもあります。
主な症状として、
- ムーンフェイス(顔の膨らみ)
- 頬、首、鎖骨上、お腹などの肥満
- 手足のやせ細り
- 手足の皮膚の薄さによる、毛細血管の浮き出し
- 皮下出血のしやすさ、無理にぶつけなくてもあざができること
- むくみ
- にきび
- 下肢の筋力低下
上記以外にも、副腎皮質刺激ホルモンによってメラニン産生が促され、色素沈着が生じる可能性もあります。
また、尿路結石、骨粗鬆症、高血圧、糖尿病などとの併発リスクも高まります。通常、腫瘍の摘出手術が行われますが、腫瘍はしばしば小さく、発見が難しくなる可能性もあります。手術で腫瘍を全て取り除けなかった際には、薬物により副腎皮質ホルモンの働きを抑制するなど、利用可能な薬を患者様の状況に考慮しながら使用していきます。
それでも症状が改善しない場合は、放射線治療も検討の余地がありますが、下垂体機能を損なわないよう、細心の注意が必要です。
この疾患は難治性のため、国からは指定難病と定められています。
似たような症状は、副腎の障害によっても引き起こされることがあり、脳下垂体に異常がない場合には、ACTH非依存性クッシング症候群と称されます。
プロラクチン産生腫瘍
脳下垂体に生じたプロラクチン産生腫瘍(プロラクチノーマ)の影響で、プロラクチン(乳汁分泌ホルモン)が過剰に放出される状態です。ただし、プロラクチンの過剰分泌は、胃薬や吐き気止め、さらには降圧剤などの薬物によるものや、ストレスによる精神的要因によっても引き起こされることがあります。そのため、血液検査でプロラクチン(PRL)の値が高くない場合には、経過観察が一般的です。
女性によく見られる疾患ですが、男性にも発生することがあります。男女共通の症状としては、骨粗鬆症が起こりやすいという点が挙げられます。
女性が罹ると、無月経、乳汁漏出(出産後以外で乳汁が分泌されること)、不妊などが主な症状となります。一方、男性が罹ると、性欲減退や勃起障害などが現れることがあり、稀に女性化乳房症や乳汁漏出が発生することもあります。
プロラクチノーマが膨大化すると、下垂体が大きくなり、視神経交差部(右目から左脳、左目から右脳への神経が交差する部分)が圧迫されて視野が狭くなることがあります。
通常、ほとんどの場合は、内服薬を使用した薬物療法が行われます。処方される薬剤には、吐き気やふらつきなどの副作用が現れやすいものがありますので、医師と相談していきましょう。
また、この疾患は国から指定難病と定められています。
非機能性下垂体腺腫
脳下垂体における腫瘍の中で、一番有名な腫瘍です。実際に全体の40〜50%を占めていると言われています。この腫瘍は良性であり、特定のホルモンを分泌しないため、多くの場合、自覚症状が乏しいことが挙げられます。
ただし、腫瘍が肥大すると、視神経が圧迫され、視野の狭窄が起こりやすくなります。さらに、腫瘍が拡大すると、正常な下垂体の部分が圧迫され、下垂体前葉が機能不全に陥り、様々な重要なホルモンの分泌が低下する可能性があります。
治療法は、手術による腫瘍の摘出が基本とされますが、下垂体からのホルモン分泌が不足している場合には、適切なホルモン補充療法も行われることがあります。
下垂体機能低下症
下垂体またはその近くに腫瘍、嚢胞、炎症などが生じ、自己免疫の変化が生じた結果、下垂体が機能障害を起こし、体内のホルモン分泌が低下する疾患です。原因疾患への治療や、ホルモンの不足を補う薬物療法が行われます。下垂体機能低下症による疾患としては、以下のものが挙げられます。
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)欠乏
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)不足により、副腎皮質から分泌されるコルチゾールというステロイドホルモンが不足します。これにより副腎不全が引き起こされ、悪化すると生体の維持が困難になる恐れがあります。自覚症状がはっきりしないため、進行に気付かないまま進行した結果、深刻化してから発見されるケースも少なくありません。主な自覚症状は、全身の疲労感、食欲不振、脱水、低血圧、低血糖、体重減少などが挙げられます。
甲状腺刺激ホルモン(TSH)の欠乏
甲状腺刺激ホルモン(TSH)が欠乏すると、甲状腺ホルモンの分泌が低下します。それにより、甲状腺機能低下症(橋本病)と似たような症状が現れます。
ゴナドトロピン(LH、FSH)欠乏
性腺刺激ホルモンであるゴナドトロピン(LH、FSH)が不足すると、男性はED、体毛(特に陰毛や脇毛)の脱落、睾丸の縮小、女性は無月経、陰毛や脇毛の脱落などが起こります。
成長ホルモン(GH)欠乏
子供の頃に発症した場合、身体全体の発育が妨げられ、低身長や血糖値が低下するなどの問題が生じます。成人の場合、成長ホルモンが不足すると内臓脂肪が増加し、筋肉量や骨密度の低下し、脂質異常症や脱水などが生じ、生活の質(QOL)が低下することがあります。
多くの場合、脳下垂体にできた腫瘍が原因であり、成長ホルモン(GH)の自己注射による治療が検討されます。
尿崩症
尿崩症は、バソプレシンというホルモンが不足することによって起こる疾患です。バソプレシンは、抗利尿作用などにより、体内から水分が失われるのを防ぐためのホルモンです。この疾患の主な原因は、下垂体の腫瘍や炎症です。
この症状には、1日中喉の渇きや乾燥感を強く感じたり、多量の水分摂取が必要になったりすることで、尿が濃縮されなくなり、多尿が生じることがあります。
この症状は、精神的ストレスなどの要因によっても引き起こされることがあり、原因を特定するためには、入院して経過を観察する必要があります。
腫瘍や炎症などの原因を除去する治療を選択しますが、原因疾患を取り除けないと判断された場合、抗利尿作用のある内服薬や点鼻薬などの薬物療法が選択されることもあります。
副腎偶発腫瘍
副腎の検査を目的としないCTやMRIなどの画像検査により、偶然発見された副腎腫瘍を指す用語が「副腎偶発腫瘍」となります。この状態には、クッシング症候群や原発性アルドステロン症、褐色細胞腫などが含まれ、悪性腫瘍の可能性もあるため、発見時には詳細な検査が必要となります。
治療は、腫瘍の性質(ホルモンの過剰分泌や減少などが見られないか)、サイズ、悪性度などを包括的に判断した上で、治療していきます。
原発性アルドステロン症
原発性アルドステロン症は、副腎皮質から分泌される一種のステロイドホルモンであるアルドステロンが過剰に分泌される疾患です。難治性の高血圧症や低カリウム血症が認められる場合、原発性アルドステロン症の可能性が疑われます。ホルモンの状態や腫瘍の有無などは、検査によって確認できます。
高血圧の患者様の中には、この原発性アルドステロン症を発症している方が20%程度いるとの報告もあり、比較的よく見られる内分泌疾患の1つです。
スクリーニング検査の結果、陽性と判定された場合には、専門の医療機関へ入院治療を受けていただきます。そこでさらに精密検査を行い、手術で摘除するか薬物療法を決めていきます。
クッシング症候群(ACTH非依存性)
副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)は脳下垂体から分泌されるホルモンです。ACTHが正常に分泌されている時であっても、副腎皮質に腫瘍が存在していると、代謝をコントロールするコルチゾールというホルモンが過剰に分泌され、クッシング病と同様の症状が出ることがあります。
しかし、下垂体からのACTHは抑制される傾向があるため、色素沈着などの兆候は見られません。
治療ではまず、副腎摘出手術が選択されます。副腎は腎臓と同じように両側に位置しており、一方を取り除いても他方が正常に機能している限り、副腎機能の低下は心配ありません。
手術が実施できない場合は、副腎皮質ホルモンの生成を抑制する薬などを使い、薬物療法を行います。
褐色細胞腫
アドレナリンやノルアドレナリンなどの「カテコラミン」を過剰に産生する腫瘍が副腎に生じる疾患です。
カテコラミンの作用により、高血圧が頻繁に起こり、急激な血圧上昇、動悸、顔面蒼白、冷や汗、頭痛などの症状が伴います。腫瘍は通常大きいため、手術で除去することが優先されますが、同時にカテコラミン過剰による症状を解消するための薬物療法も行われます。
副甲状腺機能亢進症
副甲状腺は、甲状腺に密着した小さな臓器で、甲状腺の裏側に左右各1つ、計4つがあります。一般的に、副甲状腺にできた良性腫瘍が原因で発症し、副甲状腺ホルモンの過剰分泌によって高カルシウム血症が引き起こされます。その結果、胃・十二指腸潰瘍、便秘、食欲不振、多尿、抑うつ、イライラなどの症状が起こることがあります。
まずは手術によって腫瘍を摘出することが最優先です。ほとんどの場合、手術により症状が改善されます。骨粗鬆症や尿路結石を発症している場合は、特に手術が勧められますが、何らかの理由により手術が不可能と判断された場合には、骨量を維持する治療を提案することもあります。
甲状腺機能亢進症・バセドウ病
甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される疾患の総称です。
その中でもバセドウ病は、甲状腺機能亢進症の代表的疾患とされています。主な症状としては、多汗症、食欲増進、体重減少、手の震え、動悸、突出した眼球などが挙げられます。
破壊性甲状腺炎
甲状腺には、甲状腺ホルモンを生産する球状の濾胞(ろほう)と呼ばれる微細な構造が存在します。
破壊性甲状腺炎は、これらの甲状腺濾胞が炎症によって破壊され、甲状腺ホルモンが過剰に血中に放出されることで、発熱、多汗、手指の震え、頻脈などの症状が現れます。亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎、橋本病の進行などが、破壊性甲状腺炎の典型的な疾患とされています。
甲状腺機能低下症・橋本病
甲状腺ホルモンには、新陳代謝を促進する役割があります。
橋本病は、健康的な生活を維持するために必要な甲状腺機能が低下する、主な原因の1つです。その他の原因としては、手術後の甲状腺機能低下や下垂体機能低下に関連するものなどが挙げられます。
甲状腺腫瘤
甲状腺に発生する腫瘍の95%は良性です。悪性の場合でも、甲状腺がんは進行が比較的緩やかなため、手術によってほぼ完治が見込めます。
甲状腺ホルモン異常による不妊症
甲状腺ホルモンに異常を抱える方は案外多く、日本では10〜20人に1人が甲状腺疾患を患っていることが報告されています。特に20〜30歳の比較的若い女性に多く見られますが、甲状腺ホルモンの異常は不妊の原因となるため、注意が必要です。
近年の医療現場では、不妊に悩み、相談に訪れる患者様の中に対しては、まず甲状腺機能を評価するようになってきました。
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
 古くなった骨の成分は破骨細胞の働きで壊され、骨芽細胞の働きにより、新しく生成された骨の成分に置き換えられます。しかし、ホルモンのバランスが崩れると、破骨細胞が活発になったり、骨芽細胞が弱まったりすると、骨の成分が次第に失われて、脆弱でスカスカな状態になってしまいます。これが骨粗鬆症です。
古くなった骨の成分は破骨細胞の働きで壊され、骨芽細胞の働きにより、新しく生成された骨の成分に置き換えられます。しかし、ホルモンのバランスが崩れると、破骨細胞が活発になったり、骨芽細胞が弱まったりすると、骨の成分が次第に失われて、脆弱でスカスカな状態になってしまいます。これが骨粗鬆症です。
骨粗鬆症を発症すると、慎重が縮む、腰痛、背中の痛みなどの症状が現れ、重症化すると、些細な刺激でも骨折するリスクが高まります。
特に閉経後の女性は、急激にエストロゲン分泌が減少するため、骨粗鬆症の発症リスクが高いです。
早期発見と適切な治療のためには、定期的な健康診断と骨密度検査が欠かせません。
骨粗しょう症を発症しやすいタイプ
- 偏食傾向がある方
- 糖尿病を発症している方
- 外出や運動をあまりしない方
- 日頃からお酒を多く飲んでいる方
- ステロイドを飲んでいる方
骨粗しょう症の予防・治療方法について
- カルシウムとビタミンDを適切に補給する
- 適度な運動と毎日15分程度の日光浴を行う
- バランスの良い食習慣を心がける
- アルコールの摂取を控える
治療方法としては、骨吸収をコントロールする薬、ビタミンD製剤、カルシウム製剤などの内服治療を実施します。