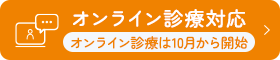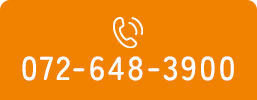血圧について
 血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁にかける圧力です。
血圧とは、心臓から送り出された血液が血管の壁にかける圧力です。
心臓はポンプのように収縮・拡張しながら、収縮すると血液を大量に送り出し、大血管の血管壁へ圧力をかけます。
心臓が収縮している時の血圧を収縮期血圧(上の血圧)、心臓が拡張して低くなる血圧を拡張期血圧(下の血圧)と呼びます。血圧測定では、この2つの血圧の結果が出力されます。
高血圧とは?
高血圧と診断される基準は、「収縮期血圧が140mmHgを上回る」ことです。同様に、「拡張期血圧が90mmHgを超えるかどうか」も1つの基準となります。これらのいずれかに合致すると、「高血圧」と診断されます。
高血圧をそのままにすると、血管への負担が増大し、動脈硬化の発生や進行のリスクが高まります。
さらに、動脈硬化は高血圧を悪化させる危険性もあります。どちらも症状がほとんどないため重症化しやすく、進行が進むと心筋梗塞や脳卒中などのリスクも上昇します。
医師の適切な診断を受け、治療を続けながら改善に努めましょう。
診察室血圧と家庭血圧の違いについて
血圧の数値は、体重と同じように、運動や入浴、食事、トイレ、ストレスなど、日常の行動によって簡単に変動します。そのため、一度だけ計測しても正確な判断はできません。血圧は、「診察室血圧」・「家庭血圧」・「24時間血圧」の3種類に分類されます。診察室血圧は「医療機関で測定された血圧」を指し、家庭血圧は「自宅で計測された血圧」を意味します。そして、24時間血圧は「特殊装置を使用して測定された血圧の変動」です。
『高血圧治療ガイドライン』における目標血圧について
日本高血圧学会は、『高血圧治療ガイドライン2019』において、各年齢層や健康状態に適切とされている血圧を以下のように決められています。
診察室血圧での目標値
| 年齢や健康状態 | 目標血圧 |
|---|---|
| 75歳未満の方 | 130/80mmHg未満 |
| 75歳以上の方 | 140/90mmHg未満 |
| 抗血栓薬を服用している方、慢性腎臓病(たんぱく尿陽性)や糖尿病の発症者 | 130/80mmHg未満 |
| 脳血管障害、慢性腎臓病(たんぱく尿陰性) | 140/90mmHg未満 |
家庭血圧での目標値
| 年齢や健康状態 | 目標血圧 |
|---|---|
| 75歳未満の方 | 125/75mmHg未満 |
| 75歳以上の方 | 135/85mmHg未満 |
| 抗血栓薬を服用している方、慢性腎臓病(たんぱく尿陽性)や糖尿病の発症者 | 125/75mmHg未満 |
| 脳血管障害、慢性腎臓病(たんぱく尿陰性)の発症者 | 135/85mmHg未満 |
近年では、診察室での血圧測定につきましては、院内での緊張の影響を受けたり、こまめな観測が難しかったりするため、家庭での血圧測定が重要視されています。毎日朝起きた時や夜寝る前など定められた時間に計測し、測定値を記録しておくことが推奨されています。この記録は診察時に医師の診断材料として活用されます。家庭での測定では、1回の測定で2度計り、両方の数値を記録するように心がけましょう。
原因は?
高血圧は、疾患や薬の影響によって生じる二次性高血圧と、原因が判明しない本態性高血圧の2つの種類が存在します。高血圧の90%は、原因となる疾患が不明な本態性高血圧で、これは、生活習慣病の一種とされています。本態性高血圧の原因については完全に明らかではありませんが、遺伝的要因に加えて、塩分や脂質の摂り過ぎ、過度の飲酒・喫煙、運動不足、肥満などの身体的要因、ストレスや疲労などの精神的な要因が組み合わさって発症する可能性があるとされています。
二次性高血圧の場合は、原因が明確なので、原因疾患の治療や原因薬の中止・変更によってコントロールできます。
一方、本態性高血圧の方は、まず悪化してしまわないように、生活習慣を改善する必要があります。食事内容や嗜好品、運動不足や肥満の解消、ストレス軽減などを見直すことが大切です。本態性高血圧を持つ患者様は、脂質異常症や糖尿病などと併発していることもよくあります。そのため、高血圧だけでなく、他の疾患の有無も確認し、総合的な治療を行うことが重要です。
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病は、進行がかなり進んでいても症状がそれほど感じにくいことがあります。健康診断などで血圧、血糖値、血中脂質値などに異常が指摘された場合、そのままにせず、必ず専門医に相談してください。
治療は?
血圧を適正な範囲に保つために、減塩やカロリー制限、持続可能な運動などの要素に焦点を当て、生活習慣の改善をサポートして参ります。
健康な日常生活を築く上では、厳密な数値に拘らず、ゆっくりと段階的に進んでいくことが大切です。
様々な努力をしても、高い血圧が持続する場合には、血圧を下げる薬を処方することも考慮しますが、薬に頼るだけでなく、生活習慣の改善が不可欠です。「薬で血圧が下がったから大丈夫」と油断せずに、継続的な努力をお願いしております。
なお、症状や状態によっては、初めから厳しい食事制限や運動療法が必要なこともあるため、当院では、患者様一人ひとりに合った治療法をご提案します。
生活習慣の見直しについて
塩分摂取の制限
 日本人の食生活では、主食として炭水化物を摂取し、副菜を通じてたんぱく質や脂肪を補うことが一般的です。しかし、近年では食の欧米化により、食事での塩分摂取量が増加しています。そのため、食事療法において塩分制限は極めて重要視されています。
日本人の食生活では、主食として炭水化物を摂取し、副菜を通じてたんぱく質や脂肪を補うことが一般的です。しかし、近年では食の欧米化により、食事での塩分摂取量が増加しています。そのため、食事療法において塩分制限は極めて重要視されています。
減塩すると、「味が物足りない」「美味しくない」と感じることがありますが、出汁を丁寧に取ったり、食材の旨味を最大限引き出したり、グルタミン酸を含むトマトなどとイノシン酸を豊富に含む肉などを組み合わせたり、香味野菜やスパイスを積極的に使ったりすることで、減塩しつつも食事を楽しみやすくなります。
推奨されている、1日の塩分摂取量は6g未満です。この数値はナトリウム含有量ではなく、食塩相当量で計算されます。ハムやソーセージなどの加工食品、漬物、インスタント食品には多くの食塩が含まれています。現在、これらの食品にはナトリウム含有量と同時に食塩相当量も表示されることが一般的ですので、ラベルをしっかり確認し、減塩の参考にしましょう。
減量する・肥満を防ぐ
 20世紀の終わり頃から広く用いられるようになった「BMI(Body Mass
20世紀の終わり頃から広く用いられるようになった「BMI(Body Mass
Index)」が、肥満など体型を示す指標となっています。BMIは以下の式で簡単に計算できます。近年の電子式体重計などは、身長を入力するだけでBMIを計算し表示してくれるものもあります。
BMI(体格指数)= 体重(kg) ÷ 身長(m)2
BMIは世界中で同じ計算式が使われますが、肥満や低体重の基準は国によって異なります。
日本肥満学会では、BMIの判定基準を以下のように定めています。
| BMI | 肥満度判定 |
|---|---|
| 40以上 | 肥満4度 |
| 35~40未満 | 肥満3度 |
| 30~35未満 | 肥満2度 |
| 25~30未満 | 肥満1度 |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 22 | 標準体重 |
| 18.5未満 | 低体重 |
毎日、決まった時間に体重を計ることやBMIをチェックし、BMI値を25未満で18.5以上に保つように体重を管理することが、生活習慣病の軽減や悪化防止に有効だとされています。
内臓脂肪型肥満だけでなく、皮下脂肪型肥満でも生活習慣病を含む健康リスクが著しく高まることが知られています。
ただし、急激な体重減少は避けるべきです。急激な減量は、皮下脂肪で保護されている血管や神経に影響を与える恐れがあります。その結果、思わぬ症状や貧血、生理不順などの問題が起こりやすくなります。
このため、日々の食事内容に気を付けつつ、適度な運動を続けることで徐々に理想の体重に近づけていきましょう。
運動は、毎日継続できる程度で、かつ適度な有酸素運動が重要です。激しい運動は、かえって健康を害することがあります。初めは1日30分ほどのウォーキングから始めてみましょう。慣れてきたら徐々に時間を延ばすことも有効です。持病のある方の場合には、運動制限が必要になるケースもあるため、運動を始める際にはかかりつけの医師にぜひ相談しましょう。
減酒・禁酒
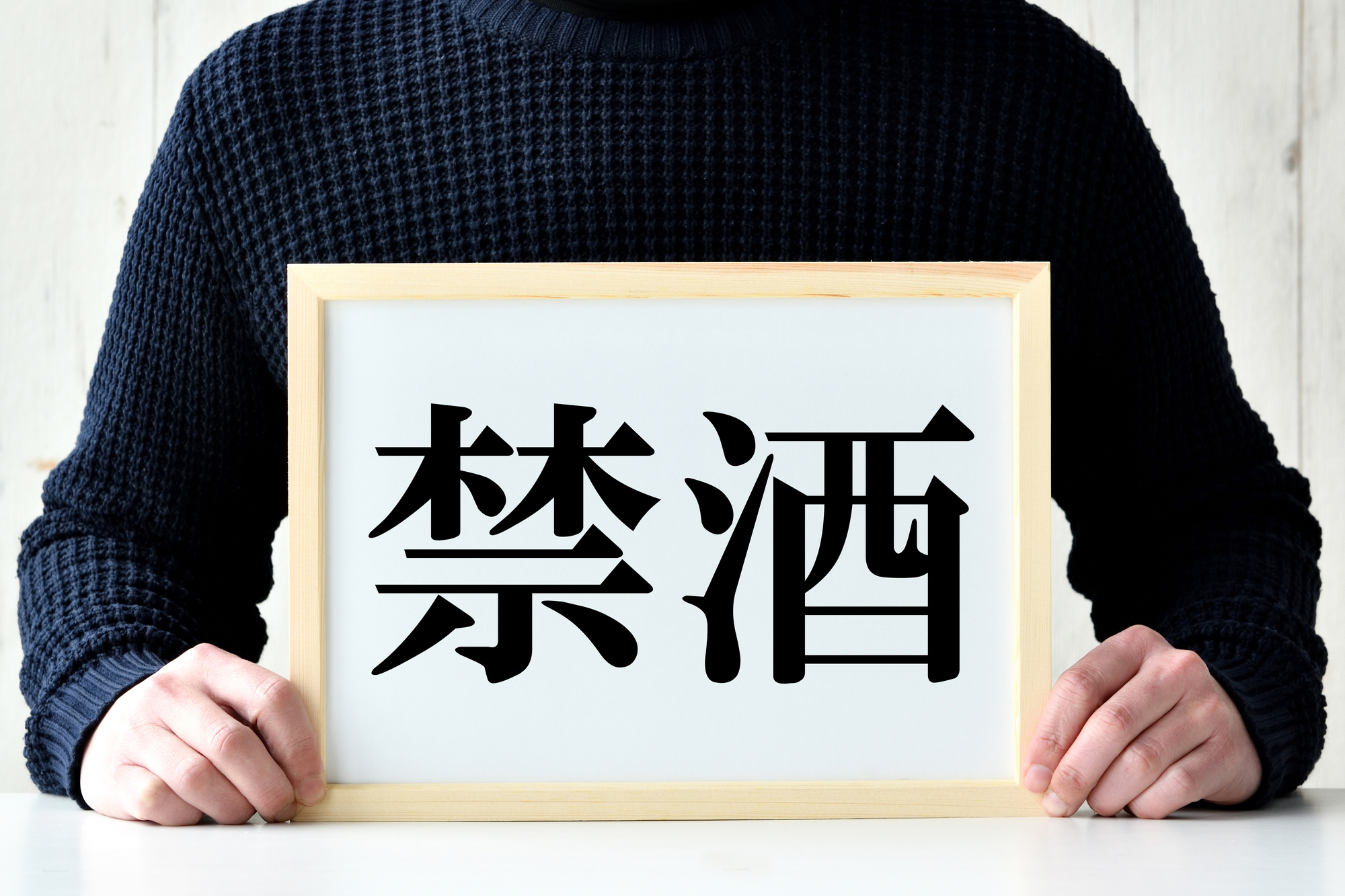 お酒を飲みすぎると、血圧上昇や肥満など、様々な健康被害に悩みやすくなります。お酒の1日の適量は、日本酒で1合、ビールの場合は500ccまでです。なお、この数値は日ごとのもので、「休肝日を1日取ったからといって、翌日は倍飲んでも大丈夫」というわけではないので、注意が必要です。
お酒を飲みすぎると、血圧上昇や肥満など、様々な健康被害に悩みやすくなります。お酒の1日の適量は、日本酒で1合、ビールの場合は500ccまでです。なお、この数値は日ごとのもので、「休肝日を1日取ったからといって、翌日は倍飲んでも大丈夫」というわけではないので、注意が必要です。
禁煙
 タバコには血管を収縮させる作用があり、さらに血圧を上昇させる要因となります。また、食事療法や運動療法を行っても、喫煙によってその効果が低下したり、呼吸器系の疾患が悪化したりするリスクもあります。
タバコには血管を収縮させる作用があり、さらに血圧を上昇させる要因となります。また、食事療法や運動療法を行っても、喫煙によってその効果が低下したり、呼吸器系の疾患が悪化したりするリスクもあります。
薬物療法について
 血圧を下げる薬(降圧剤)を使用します。血圧を下げる仕組みには様々なものがありますので、降圧剤もいくつかのタイプがあります。当院では、患者様それぞれの血圧の状態や年齢、体重、性別、ライフスタイル、他の持病の有無などに基づいて、最適な薬の種類を選んでいきます。
血圧を下げる薬(降圧剤)を使用します。血圧を下げる仕組みには様々なものがありますので、降圧剤もいくつかのタイプがあります。当院では、患者様それぞれの血圧の状態や年齢、体重、性別、ライフスタイル、他の持病の有無などに基づいて、最適な薬の種類を選んでいきます。
当院で扱う降圧剤のタイプ
| 降圧剤の種類 | 機能 |
|---|---|
| 利尿剤 | 尿を沢山作ることで血液量を減らし、血圧を下げる効果があります。 |
| 血管拡張剤 | 血管の拡張により血管壁にかかる圧力を抑制し、血圧を下げる働きがあります。 |
| 神経遮断剤 | 血管を緊張させる神経の作用を抑制し、血管を拡張させて血圧を下げる働きをしています。 |
| レニン・アンジオテンシン系薬 | 血圧を上昇させる作用を阻害し、レニンやアンジオテンシン、アルドステロンなどのホルモンの働きを抑えて血圧を下げます。 |