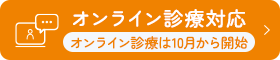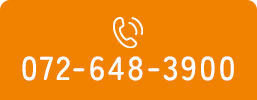甲状腺機能亢進症について
 甲状腺は喉仏の下にある内分泌器官で、体の新陳代謝をコントロールする「甲状腺ホルモン」を分泌しています。
甲状腺は喉仏の下にある内分泌器官で、体の新陳代謝をコントロールする「甲状腺ホルモン」を分泌しています。
このホルモンが過剰に分泌されると、体の代謝が必要以上に活発になり、全身にさまざまな症状が現れます。これが 甲状腺機能亢進症 です。
原因は大きく3つに分けられます。
- 甲状腺が過剰に活動してホルモンを分泌する(例:バセドウ病)
- 甲状腺に炎症が起きて細胞が壊れ、ホルモンが血中に漏れ出す(例:亜急性甲状腺炎など)
- 治療薬や一部のダイエット薬による甲状腺ホルモンの過剰摂取
この中で最も代表的なのが バセドウ病 です。
バセドウ病について
 バセドウ病は甲状腺機能亢進症の代表的な病気で、「グレーブス病」「バセドウ氏病」とも呼ばれています。
バセドウ病は甲状腺機能亢進症の代表的な病気で、「グレーブス病」「バセドウ氏病」とも呼ばれています。
人口1,000人あたり2〜3人程度と比較的まれですが、特に20〜40代の女性に多く見られます。
代謝が過剰になることで、次のような症状が出ます。
- 多量の汗をかく、暑がりになる
- 心臓がドキドキする(動悸・頻脈)
- 手の震え(小さな字が書きにくい)
- 原因不明の体重減少
- 疲れやすさ、筋力低下
- 下痢や軟便が続く
- 微熱や不眠
- イライラ・精神的不安定
- 目が飛び出すように見える(眼球突出)
- 首の腫れ(甲状腺腫大)
- 女性では月経異常・不妊の原因になることも
これらの症状は更年期障害や心疾患と間違えられることもあるため、正確な診断が大切です。
バセドウ病の原因について
バセドウ病は自己免疫疾患のひとつです。本来、甲状腺ホルモンは脳の下垂体から分泌される甲状腺刺激ホルモン(TSH)の指令に従って分泌量が調整されています。しかしバセドウ病では、体内でTSH受容体に対する抗体(TRAb)が作られてしまいます。この抗体が甲状腺を必要以上に刺激することで、甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、甲状腺機能亢進症の状態になります。
なぜ抗体ができるのかは完全には解明されていませんが、体質や遺伝的な要因、ストレス、出産などの生活環境の変化がきっかけになることがあります。この状態を放置すると、動悸・体重減少・発汗過多といった症状が強くなるだけでなく、不整脈や心不全、骨粗しょう症などの合併症を引き起こす可能性もあります。そのため、早期の診断と適切な治療が大切です。
バセドウ病の症状について
- 心臓が激しく動悸を打つ
- 多量の汗をかき、暑がりになる
- 手の震えや小さい文字を書くのが難しくなる
- 理由もなく体重が減少していく
- 体に力が入りにくくなっていく
- 疲れやすさを感じる
- 長期間下痢が続いている
- 微熱が持続する
- イライラが募る
- 眠りが浅くなっていく
- 目が突き出る
- 首が腫れる
- 月経(生理)が止まる
- 月経周期が乱れる
- 不妊症
バセドウ病の検査・診断について
 血液検査により、FT3およびFT4(甲状腺ホルモン)の高値、TSH(甲状腺刺激ホルモン)の低値、TRAb(抗甲状腺抗体)の有無などをチェックします。
血液検査により、FT3およびFT4(甲状腺ホルモン)の高値、TSH(甲状腺刺激ホルモン)の低値、TRAb(抗甲状腺抗体)の有無などをチェックします。
また、必要に応じて心電図や頸部超音波検査(当院では実施しておらず、近隣の医療機関に依頼)なども行い、甲状腺の血流状態や腫れなどを網羅的に評価し、診断をつけます。
バセドウ病の治療について
バセドウ病の治療法としては、甲状腺ホルモンの分泌をコントロールする薬物療法、放射性ヨードによるアイソトープ治療、外科手術などが挙げられます。
薬物療法(第一選択)
 甲状腺ホルモンの分泌を抑える薬を使います。軽症例や妊娠中でも使用できる場合があります。ただし、副作用に注意が必要です。
甲状腺ホルモンの分泌を抑える薬を使います。軽症例や妊娠中でも使用できる場合があります。ただし、副作用に注意が必要です。
副作用の例
- かゆみ、じんましん
- 肝機能障害
- 筋肉痛や発熱、リンパ節の腫れ
- ごくまれに「無顆粒球症候群」(白血球の一種が極端に減少する病気)
特に治療開始後2週間以内は、この副作用を早期に見つけるために血液検査が重要です。
放射性ヨウ素治療(アイソトープ治療)
放射性ヨウ素をカプセルで内服し、甲状腺に取り込ませて機能を抑える治療法です。
欧米では標準的に行われており、安全性も確立しています。
- 短期間で治療効果を得たい方
- 薬の副作用が強い方
- 再発を繰り返している方
- ごくまれに「無顆粒球症候群」(白血球の一種が極端に減少する病気)
に適しています。 ただし、妊娠中・授乳中の方や、近い将来に妊娠を希望される方には行えません。治療後は甲状腺機能低下症に移行することが多いため、その後も定期的な通院が必要です。
手術療法
甲状腺の一部を切除する治療法です。
- 薬物治療やアイソトープ治療が難しい場合
- 甲状腺の腫れが大きい場合
- 再発を繰り返している方
- 迅速に症状を改善したい場合
などに検討されます。手術後は8割以上の方が薬なしでコントロールできるようになりますが、入院や手術痕のリスクもあります。