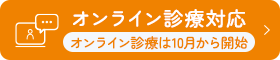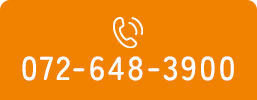- 睡眠時無呼吸症候群とは
- 主な症状
- 健康への影響
- 睡眠時無呼吸症候群の原因について
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の原因
- 睡眠時無呼吸症候群による問題について
- 睡眠時無呼吸症候群の検査について
- 睡眠時無呼吸症候群の治療について
- 日常生活で実践できる方法について
- 当院の取り組み
睡眠時無呼吸症候群とは
 睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、眠っている間に何度も呼吸が止まってしまう病気です。肥満傾向のある40~60歳代の男性、閉経後の女性に起こりやすく、強い眠気などの症状が日中の社会生活に支障をきたすこともあります。
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、眠っている間に何度も呼吸が止まってしまう病気です。肥満傾向のある40~60歳代の男性、閉経後の女性に起こりやすく、強い眠気などの症状が日中の社会生活に支障をきたすこともあります。
- 無呼吸:10秒以上呼吸が完全に止まる状態
- 低呼吸:呼吸が浅くなり、酸素が十分に取り込めない状態
これらが1時間に5回以上起こり、眠気や集中力の低下などの症状がある場合に「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。
主な症状
睡眠中に呼吸が繰り返し止まることで眠りが浅くなり、次のような症状が現れます。
- 強いいびき
- 夜間の頻回な目覚め
- 日中の強い眠気・倦怠感
- 集中力・記憶力の低下
- 起床時の頭痛や熟睡感の欠如
日常生活や仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼすだけでなく、居眠り運転などの重大な事故にもつながる危険があります。
健康への影響
呼吸が止まると、体は一時的に 低酸素状態 に陥ります。これが一晩に何度も繰り返されることで、体に大きな負担がかかります。 特に次の病気のリスクを高めることが知られています。
- 高血圧
- 心疾患(心不全・狭心症など)
- 不整脈
- 脳卒中
- 糖尿病の悪化
放置すると、長期的には 死亡リスクの上昇 にもつながることが指摘されています。
早期診断と治療の重要性
睡眠時無呼吸症候群は「放っておいてよい病気」ではありません。適切な検査と治療を受けることで、多くの方に症状の改善が期待できます。
「強いいびきをかく」「日中の眠気が強い」といった自覚症状がある場合はもちろん、ご自身では気づきにくいケースも少なくありません。実際には、睡眠中のいびきや無呼吸を家族に指摘されて初めて異常に気づく方も多くいらっしゃいます。症状をそのままにしておくと、高血圧・心疾患・脳血管疾患などのリスクを高めることが知られています。健康を守るためにも、いびきや無呼吸を指摘された際には、ぜひ早めに当院へご相談ください。
睡眠時無呼吸症候群の原因について
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が繰り返し止まってしまう病気です。 大きく3つのタイプに分けられます。
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS):気道がふさがって起こる(最も多いタイプ)
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS):脳からの呼吸の指令が出にくくなることで起こる
- 混合性睡眠時無呼吸症候群:上記2つが混ざったタイプ
この中で最も多いのは 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS) です。
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)の原因
OSASでは、睡眠中に鼻から喉にかけての「上気道」が狭くなったり、ふさがったりすることで無呼吸が起こります。気道が狭まると空気が通りにくくなり、いびきが発生し、完全に閉じると呼吸が止まってしまうのです。 主な原因には以下のものがあります。
肥満
首や喉の周りに脂肪がつくことで気道が狭くなり、最も多い原因となります。
顎の形や発育の問題
小さな顎(小顎症)や、日本人に多い顔の骨格の特徴によって、気道が狭まりやすくなります。
扁桃腺や舌の大きさ
扁桃腺が大きい、舌が大きい(巨舌症)、口蓋垂(のどちんこ)や軟口蓋が長い、なども気道の閉塞につながります。 このように、肥満だけでなく骨格や扁桃腺の大きさなどによっても睡眠時無呼吸症候群は起こるため、「痩せているから大丈夫」とは限りません。
睡眠時無呼吸症候群による問題について
日常生活におけるトラブルについて
 日中の眠気は、生活にマイナスの影響を与えます。集中力が欠けるだけでなく、仕事中や重要な会議などでも睡魔に襲われたり、居眠りしてしまったりする恐れもあります。特に、自動車を運転している時の眠気は大変危険です。実際、交通事故や鉄道のオーバーランなどで、睡眠時無呼吸症候群との関与が指摘されるケースも報告されています。
日中の眠気は、生活にマイナスの影響を与えます。集中力が欠けるだけでなく、仕事中や重要な会議などでも睡魔に襲われたり、居眠りしてしまったりする恐れもあります。特に、自動車を運転している時の眠気は大変危険です。実際、交通事故や鉄道のオーバーランなどで、睡眠時無呼吸症候群との関与が指摘されるケースも報告されています。
その他にも、抑うつ症状、不眠、そして男性における性機能障害など、様々な健康上の問題に繋がる恐れがあるため、適切な治療やコントロールが不可欠です。
疾患との関連性について
睡眠時無呼吸症候群の患者様は、下記の疾患の発症・悪化リスクが高いと指摘されています。
高血圧症
高血圧症に繋がるリスクがあるのは、閉塞性睡眠時無呼吸症候群です。閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者様の50%が高血圧症を持っており、逆に高血圧症の患者様の30%に閉塞性睡眠時無呼吸症候群が見られるとも報告されています。
特に、薬物療法が有効でない高血圧症の患者様や早朝での高血圧が見られる患者様は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群が隠れているかもしれません。閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対してCPAP治療を行うと、血圧の低下にも期待できるとされています。
心不全
閉塞性睡眠時無呼吸症候群は心臓に大きな負担をかけ、心機能を低下させるリスクがあります。
特に、心不全の患者様は、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の併発リスクが高く、閉塞性睡眠時無呼吸症候群を持つ心不全の患者様が治療を受けない場合、死亡リスクが高まると報告されています。CPAP治療を続けることで、心臓にかかる負担を軽減し、心機能低下を予防するのが推奨されています。
心血管病(虚血性心疾患や脳卒中など)
閉塞性睡眠時無呼吸症候群による低酸素血症をはじめ、交感神経の過剰な活性化は、高血圧症や動脈硬化の進行リスクを上昇させる要因になります。
また、心筋梗塞や脳卒中などの心血管障害の発症リスクも上昇させます。これらの疾患の発症により、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者様の死亡リスクが増えてしまいますが、適切な治療によって閉塞性睡眠時無呼吸症候群を管理することで、死亡率の低下も期待できます。
不整脈
閉塞性睡眠時無呼吸症候群は通常、不整脈と合併しやすく、無呼吸が増加したり、低酸素血症が悪化すれば、不整脈の頻度も高まります。
特に、夜間の不整脈は閉塞性睡眠時無呼吸症候群の患者様の約50%に見られ、重篤な閉塞性睡眠時無呼吸症候群では、その発症リスクが通常の2〜4倍に上昇すると報告されています。
睡眠時無呼吸症候群の検査について
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断には、睡眠中に「無呼吸」や「低呼吸(呼吸が浅くなる状態)」がどのくらいの頻度で起きているかを調べることが重要です。 その指標となるのが Apnea Hypopnea Index(AHI) です。 これは「1時間あたりに無呼吸や低呼吸が何回起きるか」を示す数値です。
AHIの重症度分類
- 5〜20回/時間:軽症
- 20〜40回/時間:中等症
- 40回以上/時間:重症
AHIが 5回以上 で、なおかつ眠気やいびき、熟睡感の欠如などの症状がある場合には、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
検査方法について
簡易検査(自宅でできる検査)
まず行われることが多いのが、自宅で行える簡易検査です。 センサーを鼻や指に装着して、一晩の呼吸や酸素の状態を測定します。
- メリット:ご自宅で行えるため手軽
- 結果の評価:AHIが40回以上であれば、その時点で診断が確定し、治療を開始できます
終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)
簡易検査でAHIが40回未満の場合や、診断が難しい場合に行います。 連携する専門の医療機関に一泊して、脳波・心電図・呼吸・体の動きなどを詳細に記録する検査です。
- メリット:最も精密で正確な検査
- 対象:軽症〜中等症の方、より正確な診断が必要な方
検査の流れ
- 問診・診察でいびきや眠気などの症状を確認
- 自宅での簡易検査を実施
- AHIの値に応じて診断、必要に応じてPSG検査へ
- 重症度に合わせた治療法をご提案
検査費用について
| 3割負担 | |
| 簡易検査 | 2,700円 |
睡眠時無呼吸症候群の治療について
睡眠時無呼吸症候群の治療には、症状や原因、重症度によって、最適な治療法を提案します。
CPAP療法
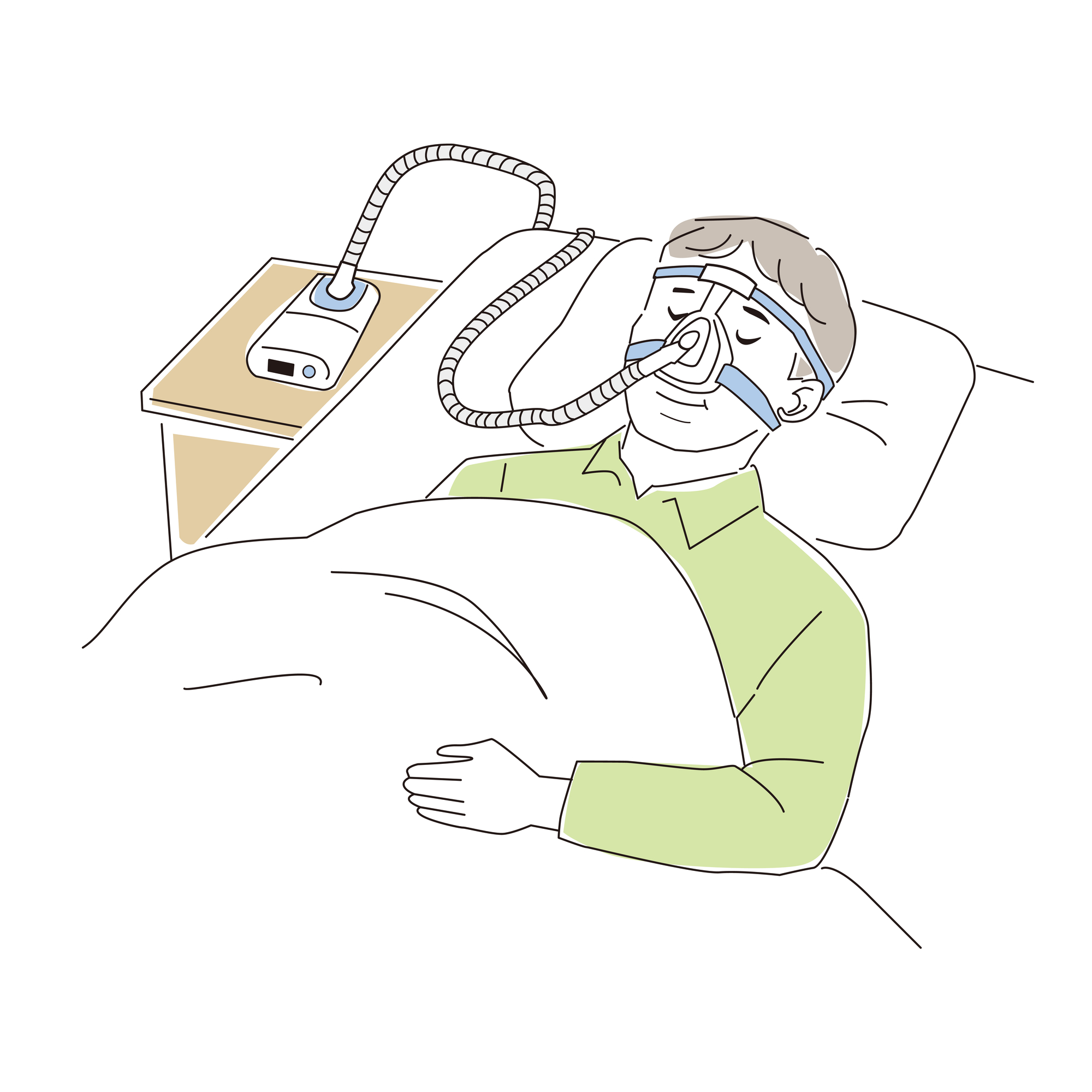 CPAP療法(シーパップ療法) は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療で最も一般的に用いられる方法です。特に 中等度から重度の無呼吸がある患者さん に効果的とされています。就寝中に鼻に装着した専用マスクから、機械を通じて空気を送り込みます。
CPAP療法(シーパップ療法) は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療で最も一般的に用いられる方法です。特に 中等度から重度の無呼吸がある患者さん に効果的とされています。就寝中に鼻に装着した専用マスクから、機械を通じて空気を送り込みます。
この空気の圧力によって気道が広がり、呼吸の通り道を確保することで、
- 睡眠中の 無呼吸やいびきが改善
- 深い眠りが得られやすくなり、日中の眠気が軽減
- 高血圧を合併している方では、血圧を下げる効果 も期待できる
といったメリットがあります。
保険適用の条件
CPAP療法は健康保険が適用される治療です。 次のいずれかを満たす場合に対象となります。
- 簡易検査で AHI(無呼吸低呼吸指数)が40以上
- 精密検査(PSG検査)で AHIが20以上
治療を始めたら
CPAP療法を続けるためには、定期的な通院が必要です。
- 機器から記録されたデータを確認
- 症状や血圧など健康状態をチェック
- 必要に応じて設定を調整
こうしたフォローを行うことで、治療効果を高め、安心して続けることができます。
生活の質(QOL)の向上
CPAP療法は適切に管理することで、眠気の改善・合併症予防・健康寿命の延伸に大きく役立ちます。「よく眠れるようになった」「昼間の集中力が戻った」と実感される方も多く、生活の質を大きく改善できる治療法です。
治療費用について
| 3割負担 | |
| CPAP治療 | 3,930円/月 |
他でCPAP治療を受けており、当院に転院を検討されている方へ
今、他の医療機関でCPAP治療を受けられている方は、紹介状をお持ちいただければ、当院で治療を続けることが可能です。
日常生活で実践できる方法について
睡眠時無呼吸症候群の治療は、CPAP療法などの医療機器による治療が中心になりますが、日常生活の工夫によって症状を軽くできる場合もあります。
1. 体重を減らす
 肥満は、首や喉の周りに脂肪がつき、気道が狭くなる原因のひとつです。
肥満は、首や喉の周りに脂肪がつき、気道が狭くなる原因のひとつです。
そのため、体重を減らすことでいびきや無呼吸が改善する可能性があります。無理のない食事管理や運動を取り入れて、少しずつ減量を目指しましょう。
2. 就寝前の飲酒を控える
寝る直前にお酒を飲むと、喉の粘膜が腫れやすくなり、気道が狭まっていびきや無呼吸の原因になります。 特に「晩酌後すぐに寝る習慣」のある方は、寝る前のお酒を控えるだけでも症状の改善を感じられることがあります。
当院の取り組み
 当院では、⽣活習慣病や循環器疾患と深く関わるSASを突然死予防の観点からも重要な疾患と位置づけています。
当院では、⽣活習慣病や循環器疾患と深く関わるSASを突然死予防の観点からも重要な疾患と位置づけています。
-
ご自宅で行える簡易検査を取り入れ、通院の負担を減らしながら早期診断をサポート
-
結果に応じて、当院での CPAP治療導入 または 専門病院での精密検査 を迅速に手配
-
糖尿病・高血圧・脂質異常症とあわせた 総合的な管理
「大きないびき」「日中の強い眠気」「熟睡感がない」といった症状は、単なる疲れや加齢ではなく、重大な病気のサインかもしれません。
気になる症状がある方は、自宅で簡単にできる検査から始められます。 どうぞお気軽にご相談ください。