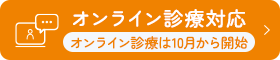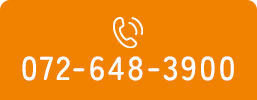ちょっと気になる”糖尿病”のお話①
こんにちは、松本ほがらかクリニック阪急高槻市駅前の渡邉です。
今日から「糖尿病ミニ知識」を少しずつ発信していきたいと思います。診療の合間に患者さんから受ける“ちょっと気になる”質問に、短く読みやすくお答えしたい、そんな思いが今回のシリーズ開始の経緯です。初回のテーマは「糖尿病ってどんな病気?」です。
糖尿病は、一言でいえば“血液の中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高い状態”が続く病気です。食事でとった糖は、膵臓から出るインスリンの働きで体の細胞に取り込まれエネルギーになります。ところが、①インスリンが足りない、②インスリンは出ているけれど効きにくい(抵抗性)のどちらか、もしくは両方が起こると血糖が高止まりします。高血糖そのものは自覚症状に乏しく、のどの渇きや尿が多い、体重減少といった分かりやすい症状が出る頃には、すでに進行していることも珍しくありません。
怖いのは“長く続く高血糖が体の隅々の血管と神経を傷つける”点です。目の病気(網膜症)、腎臓の障害、足のしびれや傷が治りにくい、といった合併症のほか、心筋梗塞や脳卒中のリスクも上がります。だからこそ、健診の空腹時血糖やHbA1c(1~2か月の平均的な血糖の指標)をチェックし、早めに気づいて治療介入することが大切です。
治療は「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の三本柱。完璧を目指すより“続けられる工夫”が大切です。たとえば主食の量と食べる順番、夜遅い間食を控える、10分のこま切れウォーキングでもOKです。小さな一歩の積み重ねで、血糖値やHbA1cは改善します。
当院では、患者さん個々の生活に合わせた現実的なプランづくりをお手伝いします。気になる数値や「糖尿病の予備軍」と言われた方も、どうぞ気軽にご相談ください。
次回は「HbA1cって何?」について解説します。お楽しみに。